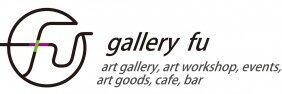9/17-9/28▷大村雄一郎、コイズミアヤ、徳永雅之、馬場健太郎、波磨茜也香、mare|PHASEーそれぞれのドローイングー
2025年9月17日(水)~9月28日(日)
12:00~19:00 日曜は17:00まで 月・火休廊
9月21日(日)15:00-16:00
ギャラリートーク「ドローイングについて」
ドローイング、それは作者の持つイメージを具現化する大切な行為
gallery fuでは、9月17日(水)から9月28日(日)まで6名の作家によるグループ展「PHASEーそれぞれのドローイングー」を開催します。今回は、自らも出展する横浜市出身の美術家、大村雄一郎氏にキュレーターを依頼、人選及び展覧会の構成を担当していただきました。
英語の「draw」は、動詞としては「引く」「描く」「引き出す」などの意味があり、ドローイング(drawing)は美術用語として一般に「線画」と訳されます。それは作家の考えをストレートかつシンプルな形で表すもので、作品制作の初期段階に行われる作業です。描く材料は支持体も含め多様であり、方法も多岐にわたります。たとえば油絵を描くための水彩や鉛筆を使ったエスキース(プランニング、下絵)であったり、立体の平面図的な役割だったと、作者の持つイメージを具現化するための重要な作業といえるでしょう。また現代においてはドローイング自体が表現の最終的な形として発表されることもあります。
ドローイングの捉え方は作家によって若干違うものがあるようです。9月21日(日)15時からは、ギャラリートーク「ドローイングについて」を開催する予定ですので、出展者のドローイングに対する考え方を詳しく知りたい方は、ぜひご来場ください。6名の作家のさまざまなドローイング表現、解釈をお楽しみください。
gallery fu代表 鈴木智惠
大村雄一郎/OMURA Yuichiro
私にとってドローイングとは、とりとめのない考えを形にする作業の過程です。 また試行でもあるため、ある程度の形になるまで同じようなものを繰り返し作ります。完成に至るまでの、つまり未完の状態の連なりだと思っています。その状態に魅力を感じます。
1964年 神奈川県横浜市に生まれる
1989年 東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒業
1991年 東京藝術大学大学院美術研究科修士課程絵画専攻修了
主な個展
2022年 space23°C/東京・等々力
2019年 gallery cafeGACA/大阪・茨木
2019年 oote41221/長野・松本
2018年 Gallery Lara Tokyo/東京・六本木
2009年 Gallery 坂巻/東京・京橋
2008年 Gallery 坂巻/東京・京橋
2007年 Gallery 坂巻/東京・京橋
2001年 Gallery Iseyoshi/東京・銀座)
1998年 トキアートスペース/東京・外苑前)
1997年 ルナミ画廊/東京・銀座
1994年 ルナミ画廊/東京・銀座
1993年 藍画廊/東京・銀座
1992年 ルナミ画廊/東京・銀座
1989年 田村画廊/東京・神田
1988年 ギャラリー21/東京・銀座
主なグループ展
2023年「9 stories 2022-2023 」ギャラリー605/東京・六本木
2023年「目利きが選ぶmy favorite 」 FEI ART MUSEUM YOKOHAMA /神奈川・横浜
2023年「5 rosettes 」ギャラリー605/東京・六本木
2023年「CUE」スペース461/広島・福山
2023年「OPERA」カフェロンド/広島・三原
2023年「位置のエクセサイズ-II」DHARMA沼津/静岡・沼津
2015年「3人展」Gallery Lara Tokyo/東京・六本木
2009年「Small Collections」Gallery 坂巻/東京・京橋
2008年「Drawing」Gallery 坂巻/東京・京橋
2007年「space objects show」Gallery 坂巻/東京・京橋
2000年「VOCA展2000 」上野の森美術館/東京・上野
1999年「下総屋商店落花生工場跡美術展」千葉・酒々井
1998年「芝山野外アート美術展」芝山観音教寺/千葉・芝山
1994年「神奈川アートアニュアル94」神奈川県民ホール/神奈川・横浜
コイズミアヤ/COIZUMI Aya
世界の成り立ちやその仕組みについて観察し、見えている/在る(と思っている)ものを、異なる在り方にうつしかえて確認してみるような制作をしています。数学の結び目理論の各種構造を借りて紐のドローイングをしたり、塊から紐を木彫するシリーズからの出品です。
1971年 東京生まれ
1994年 武蔵野美術大学造形学部空間演出デザイン学科卒
2009年〜新潟県長岡市在住
主な個展
2025年「箱と本」ガレリアポンテ/金沢市
2024年「箱と紐と本と」Flat River Gallery/東京
2023年「重なることについて」obi gallery/藤沢市 ※会期は2024まで
2023年「本の似姿二〇二三」FRAGILE BOOKS Open Day/東京
2022年「かさなりとかたまり」楓画廊/医学町画廊/新潟市
2022年「うつしかえと結び目のはなし」ギャラリー椿・GT2/東京
2021年「やわらかな座標」ぎゃらりーみつけ展示室1・2/新潟県見附市
2020年「組み立て/空間と量について」ガレリアポンテ/金沢市
2020年「結び目のはなし」楓画廊/医学町画廊
2018年「つづくうつしかえ」GALLERY RO-BA-YA/新潟市
2017年「かさなりとかたまり」Kaede Gallery + full moon/新潟市
2017年「かさなりとかたまり mini」忘日舎/東京
2016年「うつしかえ」ガレリアポンテ/金沢市
2016年「うつしかえ」GALLERY RO-BA-YA
2015年「充満と空虚」文学と美術のライブラリー・游文舎/柏崎市)
2014年「箱の仕事・旧作を振り返って」 Kaede Gallery + full moon
2014年「容量と天体」GALLERY RO-BA-YA
2012年「冷たい小品集」GALLERY RO-BA-YA
2011年「組み立て/Overflow(コップの水があふれる様について)」 ギャラリー椿
2010年「隣の部屋」「monad」画廊 編/大阪
2010年 ギャラリーmu・an/長岡市
2010年「遠くに行って 帰ってくる。」GALLERY RO-BA-YA
2009年「隣の部屋」ギャラリー椿・GT2/東京
2008年「瘡蓋の中」Gallery Jin/東京
2007年「身体という家」松明堂ギャラリー(新作家たち selection展)/東京
2007年「山と隧道と内臓腔」ぎゃらり かのこ/大阪
2005年「山と隧道」ギャラリー椿・GT2/東京
2005年「充満と空虚」ギャラリー椿/東京
2005年「充満と空虚とひとつひとつの小さな通路」 画廊 編/大阪
2004年「山と隧道」 楽風/浦和
(他、グループ展多数)
美術館での展示
2013年「空想の建築ーピラネージから野又穫へ−」町田市立国際版画美術館/東京
2003年「体感する美術2003」佐倉市立美術館/千葉
2001年~2002年「BOX ART」リアス・アーク美術館、新潟市美術館、おかざき世界子ども美術博物館、静岡アートギャラリー、高知県立美術館を巡回
主な収蔵
東京オペラシティアートギャラリー(寺田コレクション)
新潟県立近代美術館
徳永雅之 /TOKUNAGA Masayuki
エアブラシを使ったペインティングと並行して、様々なアプローチでドローイングを描いています。前者は粒子の集積、後者は線描を扱い表現の可能性を探っています。
1960年 長崎県佐世保市生まれ
1985年 東京芸術大学美術学部絵画科油画専攻卒業
1987年 東京芸術大学大学院美術研究科(修士課程)壁画専攻修了
主な個展
2025年 ギャラリーマール/東京
2024年 ギャラリーマール/東京
2023年 ぎゃらりー由芽/東京
2022年「monochrome and drawing works」gallery shell102/東京
2022年「Particles from 1991 to 2020/前期・後期」kaneko art gallery/神奈川
2021年「粒子の向こうへ -Beyond the particles-」kaneko art gallery/神奈川
2020年 ぎゃらりー由芽/東京
2020年「オープニング展ーⅡ」kaneko art gallery/神奈川
2019年「the scene of light」gallery shell102/東京
2019年 美容室cotton/埼玉
2018年 ぎゃらりー由芽/東京
2018年「painting and drawing」ギャラリー美の舎/東京
2017年「painting and drawing」ギャラリー枝香庵/東京
2017年 FLAT FILE SLASH/長野
2017年 ART TRACE GALLERY/東京
2016年 SAVOIR VIVRE/東京
2016年 ぎゃらりー由芽/東京
2014年 ART TRACE GALLERY/東京
2013年 Art Space 88/東京
2012年「The Scene of Light」KTNギャラリー/長崎
2012年「The Scene of Light」ギャラリー枝香庵/東京
2011年「The Scene of Light」ギャラリー健/埼玉
2008年 GALLERY APA/名古屋
2007年 ギャラリーEL.POETA/埼玉
2005年 ギャラリーEL.POETA/埼玉
2004年 庭園ギャラリー櫻守/埼玉
2003年 ギャラリーEL.POETA/埼玉
2003年 かねこ・あーとギャラリー/東京
2002年 ギャラリーEL.POETA/埼玉
2002年 かねこ・あーとギャラリー/東京
2001年「MONOCHROME WORKS」ギャラリーEL.POETA/埼玉
主なパブリックコレクション
2025年 ゲートホテル福岡
2022年 JTOWER 新オフィス/東京
2018年 リッツカールトン西安/中国・西安
2017年 ソラリア西鉄ホテル京都プレミア三条鴨川/京都
2008年 パークハイアット上海/中国・上海
2004年 日本サムスン株式会社(プライベートコレクション)/東京
2001年 エンターテインメントクルーズ船「ROYAL WING」/神奈川
2000年 特別養護老人ホーム「さくら」エントランスホール壁画/東京
(他、個展、グループ展多数)
著書
2008年「Tayutau テルミンの小品と光の絵画 溝口竜也+徳永雅之」(共著)/冬青社
馬場健太郎 /BABA Kentaro
制作を始めた頃からキリスト教美術の在り方が、常に頭のどこかにあったように思います。そこには、「威厳に満ち堂々としたもの」が立派な美術であるということに対する居心地の悪さを感じていたように思います。
2024年の秋。僕は生まれ故郷の長崎市から車で2時間ほどの平戸方面に小さな旅行に出かけた。途中、隠れキリシタンの里、外海町(そとめちょう)を巡り、キリシタン禁教から解放された明治期から大正期 昭和初期に建築された素朴な教会群を見てまわった。そこには、日々の暮らしの中に祈りがあり、質素な佇まいの小さな教会は、どれも丁寧な作りで美しかった。強い信念を持ち「いのる」人たち。ひっそりと佇む教会。そんな在り方に強く心打たれた。今、こんな風に絵を描きたいと思っている。
ドローイングの中でこんな風にひっそりとしかし、したたかに佇む小さな教会のような有り様の「線」や「形」が出て来てくれたらと思っている。
1968年 長崎県長崎市生まれ
1993年 創形美術学校研究科造形課程修了(修了制作作品・高澤賞受賞)
1995年 第10回ホルベインスカラシップ奨学
2005年 文化庁芸術家在外派遣研修員としてミラノに滞在国立ブレラ美術学校にて研修
主な個展
2025年「紙の上のいのり」ティル・ナ・ノーグギャラリー/東京
2023年「いろのかたち」ティル・ナ・ノーグギャラリー/東京
2019年「記憶と忘却のあいだ」鎌倉画廊/神奈川
2018年「Layeredvision-Brush with the invisible」ティル・ナ・ノーグギャラリー/東京
2016年「Scenes Beyond 」ティル・ナ・ノーグギャラリー/東京
2013年「無想」鎌倉画廊/神奈川
2010年「鐘楼の追憶」鎌倉画廊/神奈川
2008年 アートフロントギャラリーグラフィックス/東京
2007年「西からの風」ギャラリーMOMO/東京
2005年「LA STRADA」もみの木画廊/東京
2004年「Blue on Red 」トキアートスペース/東京
2003年「 Presence 」リストランテ ビーチェ/東京
主なグループ展
2019年「stories -Porto and Nagasaki 」 ポルトガル
2018年「This Side of Paradise 」韓国 安養芸術文化財団記念館
2018年「IMAGO MUNDI / Luciano Benetton Collection 」イタリア
2016年「works on paper at fog linen work 」東京
2014年「Inner Scenery 」CHIAKI KAMIKAWA CONTEMPORARY ART/キプロス
2012年「Spring of Joy 」展 Gallery EM 長崎
2009年「二つの扉」展 庭園ギャラリー櫻守 埼玉
2008年「絵画の春」展 鎌倉画廊/神奈川
2003年「相貫するまなざし」トキアートスペース/東京
2002年「Art Scholarship 2001 現代美術賞」exhibit LIVE/東京
2001年「流れとよどみ」文房堂ギャラリー/東京
2000年「VOCA展2000現代美術の展望—新しい平面の作家たち」上野の森美術館/東京
2000年「第5回昭和シェル現代美術賞展」 目黒区美術館/東京
(他、個展、グループ展多数)
アートフェア
2025年「アートフェア東京」日本・鎌倉画廊
2024年「Kiaf + seoul 」韓国・ 鎌倉画廊
2023年「Kiaf + seoul 」韓国 ・鎌倉画廊
2022年「Kiaf + seoul 」韓国 ・鎌倉画廊
2019年「art3f BRUXELLES 」ベルギー ・鎌倉画廊
2018年「 YIA ART FAIR 2018 Paris 」フランス
受賞
2004年 第8回ADSP(Art Document Support Program by SHISEIDO)選出
2000年 第5回昭和シェル現代美術賞展/審査員賞本江邦夫賞受賞
コミッションワーク
東京會舘 箱根ハイアットリージェンシーなど国内外多数
波磨茜也香 /HAMA Ayaka
少女をモチーフにした作品を中心に制作。現在、自身が発見、感動したモノ・コトや持病(大した事無い)等をテーマに制作中。
明日自分にも起こりそうな出来事を描いていきたい。
1991年 横浜生まれ
2015年 多摩美術大学絵画学科油画専攻卒業
主な個展
2022年「AYAKA HAMA × HAMABE × space Yuu ~浜辺のドローイング」space_yuu ページ内にて(web上展示)
2021年「VINYL SHOWCASE AYAKA HAMA Solo Mini Exhibition 『A SOAKING GIRL』」JR東京駅構内 グランスタ東京 1F VINYL内・VINYL GALLERY
2020年 波磨茜也香個展「Air Max Hunting」space_yuu ページ内にて(web上展示)
2016年 波磨茜也香個展「AYAKA HAMA AUTUMN/WINTER COLLECTION 2016-2017 - Armpit sweat -」渋谷公演通り MODI 6F・HMV&BOOKS TOKYOレジカウンター前 特設スペース
2015年 波磨茜也香展「今、事の重大さに気付きました」ヴァニラ画廊
2014年 波磨茜也香展「私は非常に気分が良いです」ヴァニラ画廊
主なグループ展
2025年「THE MONOCHROME SET – モノクロームの少女たち」アートコンプレックスセンター
2025年「中空工房 SOFVI EXHIBITION」高知 蔦屋書店
2024年「VINYL exhibition」代官山 蔦屋書店2号館 1階 アートフロア
2024年「mini SOFVI series POPUP」JR東京駅構内 グランスタ東京 1F VINYL
2024年「VINYLS exhibition」OIL by 美術手帖ギャラリー(渋谷PARCO)
2023年「VINYL show」MORI ART MUSEUM SHOP 森美術館 ショップ六本木ヒルズ ウェストウォーク
2022年 めろっこめろこ・波磨茜也香・熊谷晴子 3人展 「INCIDENT」 MASATAKA CONTEMPORARY
2019年「ミッドナイトストアー+THE blank GALLERY present『ザ・プレミアム平成ショー』」 THE blank GALLERY
2018年「save point」多摩美術大学 絵画北棟 4F 405
2018年「秘蜜の花園」MASATAKA CONTEMPORARY
2018年「Flowers」馬車道 大津ギャラリー
2016年「MIDNIGHT LIBRARY the first half of 2016 artists EXHIBITION- ミッドナイト・ライブラリー 2016 上半期アーティスト展」渋谷公演通り MODI 6F・HMV&BOOKS TOKYOレジカウンター前 特設スペース
2016年「O’YA展Ⅴ」MONDAY ART SPACE
2016年 緊急開催!! 熊本地震被災地支援展示 「アートの力の見せ所!」銀座モダンアート
2015年「Condensed Vanilla 2015 ヴァニラ画廊セレクション」ヴァニラ画廊・展示室AB共通
(他、グループ展多数)
連載
2019年~「 波磨茜也香のおんなのこ散歩 」@ROADSIDERS’ weekly
公募/受賞歴
2014年 トーキョーワンダーウォール公募2014入選
2013年 第二回ヴァニラ画廊大賞 大賞
mare /マレ
私の作品は、「記憶」と「時間」、そしてそれらが静かに交差する層の中で生まれます。
幾重にも塗り重ねたアクリルを削り出す過程は、見えなくなった出来事や感情の痕跡を掘り起こすような行為です。
その中で現れるかたちや色彩は、意図を超えて立ち現れるものであり、私は自らの手を通して現れるものに耳を澄ませながら、ただそっと伴走する感覚で制作を続けます。
時間は直線ではなく、重層的で可逆的なものとして私の中に存在しています。
過去が未来を照らし、未来が過去を包み込むような感覚。
削るという行為は、そのすべての時間が幾層にも重なった構造を浮かび上がらせ、それ自体が私にとって癒しの行為であり、静かな対話の時間でもあります。
私にとって作品とは、ある地点に現れる痕跡であり、その痕跡が誰かの記憶や感情と、ある種の共鳴を起こすことを願って制作しています。
完成された作品は、制作中に交差した時間や感覚の残響であり、それが見る人にとって、何か名づけようのない力として作用することを信じています。